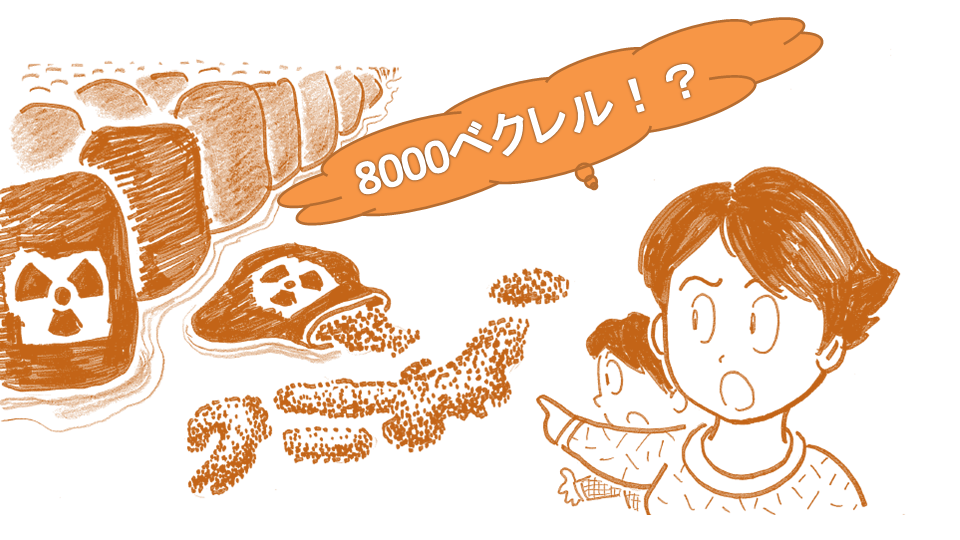2016年4月28日 朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASJ4T4T0WJ4TPTIL016.html
チェルノブイリ原発事故後のベラルーシと現在の福島で危険な「安全」キャンペーンが繰り返されている――。フォトジャーナリストの広河隆一さんはそう指摘した(「核の神話:22」で紹介)。その中心にいるのは国際放射線防護委員会(ICRP)副会長のフランス人、ジャック・ロシャール氏だという。ロシャール氏はベラルーシで「エートス」と呼ばれるプロジェクトを指揮し、今は頻繁に福島を訪れている。
◇
■福島県立医科大主催で3月8日に開かれた「東日本大震災・福島原発事故5年国際シンポジウム」でのロシャール氏の発言要旨
この5年間、福島についての様々な活動やIAEA(国際原子力機関)などの国際機関が開く会合、日本の組織や専門家らが開く会合に参加してきました。日本の多くの人々や組織と、深く特別な関係を築くことができました。福島県立医科大との実り多い協力、特に伊達市や住民団体「福島のエートス」は我々の活動に非常に協力的でした。
チェルノブイリ事故の経験とともに、これからICRPが出す勧告には、福島のあらゆる教訓を盛り込もうと考えています。ICRPは福島の人々とともにあります。
私自身がこの問題に関わり始めたのは1990年夏、IAEAの国際チェルノブイリ・プロジェクトを通じてでした。原発30キロ圏からの住民避難のコスト・ベネフィット(費用効果)を分析するのが任務でした。その時、私の放射線防護の科学は、住民の疑問や不安にはあまり役立たないと感じました。
そのあと、キエフからミンスク行きの夜行列車で乗り合わせた地元の若い男性と話し込みました。彼が「(フランス人の)あなたたちが一体ここで何をしているのですか」と尋ねてきたので、チェルノブイリ事故関連の仕事で来たと告げました。そうすると、彼は自問するようにこう言ったのです。「この地域の女性とは、結婚できないでしょう」。私は大江健三郎氏の本などを読んでいたのでピンときました。広島への原爆投下後に起きたこと(差別)が起きようとしている。これが私にとっての転換点になりました。
*
90年代半ばから、「エートス」と、それに続く「コール」プロジェクトをベラルーシで進めました。汚染地に暮らす住民の生活環境改善をめざすものです。放射線にどう対応していいのか分からず、住民らは日常生活のコントロールを完全に失っていました。
当初は住民らから懐疑的な目で見られましたが、一緒にワーキンググループをつくり、子どもの防護や牛乳など食品の安全性への懸念を共有しました。我々のアプローチはとてもシンプルなものでした。まずは注意深く住民らの話に耳を傾ける。次に、現状についての理解を共に深めるため、森や環境の放射線測定を実施する。そして放射線量の低減とともに住民の生活環境も改善する。最後に住民と地元の行政当局とをつなぎます。
最初に訪れたオルマニー村は当局とのつながりが切れて孤立していました。後に村人が言うには「あなた方が村にやってきた時には懐疑的でした。原発事故後、科学チームが入れ代わり立ち代わりやってきて放射線の測定をし、村人に質問しては、去っていく。そして二度と彼らと会うことはない」と。我々はそのメッセージの意味を受け止めました。
ベラルーシの教訓は、事故後の人間的側面です。行政当局が住民の信頼を失い、慣れ親しんだ環境から切り離される。家族や社会の崩壊、将来への不安、差別……。住民は日常生活のコントロールを失い、自立できなくなる。しかし、レジリエントな(回復力ある)少数の人々が状況を改善するものなのです。
福島でもベラルーシと同じような人間的側面の教訓が得られました。福島でのダイアローグの内容はICRPと「福島のエートス」のウェブサイトで共有しています。
 |
| ジャック・ロシャールさん=福島県立医科大、田井中雅人撮影 |
◇
■国際放射線防護委員会(ICRP)副会長ジャック・ロシャール氏
福島県立医科大での国際シンポジウムに参加したロシャール氏に、福島在住のジャーナリスト・藍原寛子さんとともに話を聞いた。
――福島に関わるようになるいきさつは。
「(チェルノブイリでの)私の経験を伝えてほしいと頼まれて、福島に来るようになりました。福島のエートスの関係者から電子メールで私に協力依頼があったのです。11年9月に日本の環境省主催で、私の講演会が東京で開かれたのがきっかけでした」
――ベラルーシと福島で活動されて、その違いはどういうところにあるでしょうか。
「30年前と今とでは技術が違い、初動対応はより迅速になっています。さらに日本の経済力はベラルーシとは比べものにならない。(1986年のチェルノブイリ事故は)ソ連が崩壊寸前の時期でしたので、復興は極めて難しかったのです。(ベラルーシでは)原発30キロ圏内から住民が避難し、(土地は)捨てられたのですが、福島は違います」
――あなたが唱える「放射線防護文化」とはどういうことですか。
「人々が日々、放射線を扱う能力のことです」
――ベラルーシにその「文化」を導入したのですか。
「いいえ。ベラルーシの人々と活動するなかで我々が学んだのです。当初は科学者として現地に赴き、状況を評価しました。住民らはコントロールを失い、途方にくれていたのです。それを取り戻すお手伝いをしようと、エートス・プロジェクトを始めました。96年から5年かけて住民らと活動するうちに、この放射線防護文化が立ち現れたのです」
――事故から30年たった現地の状況は。
「我々が活動を始めたオルマニー村を昨年9月に訪ねました。住民らはリラックスして暮らしていました。我々が活動しなかった隣の村では何もできていませんでした」
――現地の避難の基準を教えてください。
「現地当局は91年に年間5ミリシーベルト以上の線量では居住を薦めない方針を決めました。農業が続けられるかどうかなど、村ごとに状況は違いますが、5ミリシーベルト以上の場所からは避難させる決断をしたのです」
*
――福島について年20ミリシーベルトでも帰還という日本政府の方針はどうでしょうか。
「20という数字と現実のデータに大きな差があることが問題です。20は福島での事故の直後に決められたもので、いまではほとんどの場所の線量はずっと低くなっています」
――内部被曝(ひばく)についてのご見解は。
「もちろん、外部被曝(ひばく)と内部被曝(ひばく)を併せたトータルでの値です」
――日本政府の(帰還)基準20ミリシーベルトは妥当ですか。
「年20ミリだとすれば多すぎる。現実に基づいているというより行政用の数値でしょう」
――東日本大震災・福島原発事故5年のシンポジウムに参加した感想を。
「2011年9月に初めて来た時、日本の人たちがアドバイスを求めていると感じました。今では我々の方が耳を傾け、学んでいます。福島の声はより強くなったと感じます。住民らは、どこに向かいたいのかが分かっています。多様性や様々な考え方を受け入れています。と同時に、シンポジウムで登壇した福島のみなさんは、他者に対する深い理解をしていることに感銘を受けました。シンポの議論では、ほとんど数字が出てこなかった。5年前は数字だらけの発表ばかりでした。科学的根拠がどうだとか。今日は人間の側面に焦点が当たっていました」
「原発事故は放射線管理の問題です。有害なものになりえます。しかし、我々は科学者として、これはそれほどの問題ではないと人々に理解してもらう手助けができるのです。福島ではほとんどの場所で(放射線の)問題はなくなっている。もちろん、住民には逆境やストレスに耐える力が必要です。地元に戻って自立したい人々を助けることができればと思っています。原発事故は社会や個人を強く揺るがしました。放射線量や汚染度だけでなく、人間の問題として注意深く見ていくことです。福島の人々から私が多くを学んだように、将来また事故が起きた時に備えて、何をしなくてはならないのかがわかるのです」
――次の事故に備えるというのですか。
「私は90年からチェルノブイリ周辺で原発問題に関わり始めました。いつの日か、また事故が起きる。もちろん起こらないほうがいいが、起こるかもしれない。その時、何が問題になるのかを伝えるのは、プロとしての我々の責任です。チェルノブイリ事故後、我々の話を聞いた住民らは懐疑的だったが、福島で事故が起こった。福島の後にも事故が起きるか起きないかは、だれにも分かりません」
――今日の議論に数字が出てこなかったとおっしゃいましたが、なぜだと思いますか。
「シンポジウムの目的が数字についての議論ではなかったからです。この5年間、何をしてきたかが問題なのです」
――数字を出すと、住民らが恐れるからではないですか。
「そうは思いません。人々のまわりには数字があふれています。いろいろな文書にも、新聞にも。福島についての数字や多くの情報があふれています」
――福島県民健康調査によると、167人が小児甲状腺がんと診断されました(うち良性1人)。検討委員会の星北斗座長は記者会見で「事故による放射線の影響とは考えにくい」と述べています。あなたのご見解は。
「まず言わなくてはならないのですが、私は甲状腺がんの専門家ではありません」
――著名な専門家らが「福島の小児甲状腺がんの発生は放射線の影響とは考えにくい」と言うのをどう思いますか。今日の議論では放射線や原発への批判が一切出てきませんでした。福島で何が起きているのでしょうか。
「原発事故がありました。土地が汚染されました。人々は被曝(ひばく)しました。そして、福島はチェルノブイリほどのインパクトはないという科学的要素があります。ベラルーシ、ウクライナ、ロシアでは、事故から何年かたってから甲状腺がんの多発が見られ、ずっと後に科学的に放射線との因果関係が認められました。福島では予防措置として、日本政府が子どもたちの甲状腺検査を決めました。チェルノブイリの経験があったからです」
――チェルノブイリでも事故5年後の時点では放射線と甲状腺がん多発との因果関係は認められていませんでした。10年後にようやく認めたのです。福島もそうなりませんか。
「チェルノブイリで甲状腺検査を始めたのは事故から何年もたってからでした。甲状腺がんが増えるとは誰も予測していなかったからです。何年もたってから一部の医師たちが問題に気づいたのです。甲状腺がんの子どもが1人、2人、3人と増えるにつれてです」
――地元の医師たちは検査結果をIAEAのチェルノブイリ調査団長を務めた故・重松逸造氏らに見せたけれども、なかなか因果関係を認めなかったということです。
「私をディベートに巻き込もうというのですか。これについて議論したくありません」
*
――福島で何が起きているか。チェルノブイリと比較していかがでしょう。
「チェルノブイリほどの放射線量ではありません。人々を検査するアプローチも違います。福島では極めて初期に行われたのです。世界中の科学者が認めるように、がんの発症は様々な要素に起因します。放射線だけではない。私は専門家ではないですが、現在のところは少し様子を見ましょう、ということです。福島県立医科大は最善を尽くしていると思います。ちょっとやりすぎかもしれませんが、おそらくやるべきことをやっています。それが彼らの責任です。原発のせいだと結論を急ぐ前に、あと2~3年待って、様子を見て、状況が明確になるのを待つべきです」
――待つ時間はないでしょう。日本政府は20ミリシーベルトでも大丈夫だからと、避難民に帰還するよう促しています。
「また、20ミリシーベルトの問題ですか。あなたもよく分かっているように、年間20ミリシーベルトも被曝(ひばく)するはずはありません。それは5年前に導入された行政的な数値です」
――日本政府がいうところの20ミリシーベルトは誇張されているということですか。
「誇張されているわけではありません。5年前に行政が導入した数字です。いま汚染地の住民が受けている放射線量は低くなっています。年1ミリ以下、最大でも数ミリでしょう。そういう状況でも帰還できない人々に対する(許容)線量を考える中で、数ミリから10ミリという数字が出てきたが、(ICRPの関係者は)だれも20ミリなんて言っていないのです」
――内部被曝や被曝による健康影響が出る「しきい値」についてのお考えは。
「しきい値はないというのが、放射線防護の基本です。科学的根拠がないからです」
――ICRPは一定の許容線量を指標として薦めています。
「ICRPが薦めているのは、これを越えないようにしてほしいという数字です。ICRPの主要勧告は、被曝線量を合理的にできるだけ低くすることです。これがICRPのキーメッセージです」
――日本政府がICRPの勧告を取り違えているということですか。
「そうではありません。11年の福島事故後、(09年に発表した)ICRP勧告を読んだ(日本政府の)人たちがそれぞれに独自に解釈して、そうした数字を使うことにしたのでしょう」
*
――「エートス」プロジェクトについておうかがいします。現地取材したあるジャーナリストは「ベラルーシではエートスは失敗した」と言っています。住民らの信頼を、おそらくあなたが得られなかったからだというのです。どう受け止めますか。
「あなたがたもジャーナリストだったら、ベラルーシに行って、自分の目でごらんになったらいかがですか。我々が関わった村のリストをお渡しします。なんの圧力もかけられないでしょう。ただ現地へ行って、村人たちに聞いてみられたらいいでしょう」
――エートス・プロジェクトはうまくいったということですか。
「なにも言いません」「ジャーナリストとして自分の仕事をして下さい。これは裁きではないのですから。ネット上では、確かに私は『犯罪者』ですよ」
――そんなことはないでしょう。(エートスは)福島で再起を図るということですか。
「いいえ。ただ、ベラルーシへ行って、住民と話して、あなた自身で決めてください。私の立場やエートスが何をしてきたかについてはご存じでしょうから。(チェルノブイリ原発事故で)めちゃめちゃになった被災者らが自立を取り戻すのに役だったという意味では、(エートスの活動は)大成功でした」
――福島県民の中でもエートスの活動に批判的な人からは「データはとられるが、治療はしない。実験材料にするな」との声もあります。
「我々は完璧な世界に生きているわけではありません。個人的には、検査をする時には住民と情報を共有し、検査結果について議論します。私のメッセージは、真摯(しんし)に人々と活動することです」
*
――(福島の)住民の治療をするのはだれですか。
「我々、専門家のだれかです。その人たちを尊重し、扱うのです。(エートスが)被災地の人々をモルモットにしているという批判があることは知っています。人々に自立心を与えながら、汚染地にとどまり続けるように強いている、と。そういう議論があることは分かっています」
――シンポジウムで、福島県立医科大の専門医もこう発言していました。「なぜ、嫌がる子どもたちに甲状腺検査をしなければならないのか、理由がはっきりしていない」。検査を続ける一方で、小児甲状腺がんが出ている理由について明確な説明がされないことに混乱が広がっているようですが、ご見解は。
「繰り返しますが、私はそれについての専門家ではない。世界のすべてのことに通じているわけではありません」
――ICRPは福島でどういう役割を果たしているのでしょうか。
「まず、日本でのICRPの役割は、我々の勧告を日本人に理解してもらう手助けをすることです。福島での事故のあと、日本から多くの質問が寄せられたからです。それが、この勧告(出版物)です。ICRPは規制をかける機関ではありません。最善の科学的証拠に基づいて一般的な勧告をするだけです」
――ICRPとあなたの「エートス」の活動には、フランスの原子力産業界から資金が拠出されているのですか。
「話はここまでです」
――ウェブサイトによると、エートスはフランスの原子力産業界から資金が出ているという情報があります。事実ですか。
「そうです。言ったように私は『犯罪者』です、ウェブサイトでは」
――「福島のエートス」にも、あなたの資金が流れていますか。何か利害の衝突があるのですか。
「利害の衝突、いや、そういうことは無視します。いいジャーナリストでありたければ、ベラルーシに行って、我々が10年、15年と活動した村で、住民らにインタビューすることです。うわさや攻撃の類いを利用するのはやめることです。ネットにはこの20年、不適切な原発事故の情報があふれています。問題は、私が原子力推進か否かや、原子力産業やロビーから資金をもらっているか否かではなく、原発事故の汚染地に捕らわれの身になって被曝している人がいることなのです。だれがそういう人々を助けるのですか」
――その原発事故の被災者の中に「原子力産業のお金とは関わりたくない」という意見があるとすれば、どう思いますか。
「いかなる意見も尊重します。原子力に反対する人もいます。問題は、汚染地に暮らしている人たちがいて、彼らはそこに暮らし続けたいのです。であれば、彼らが自分の身を自分で守る術を教えてあげるのが義務でしょう。避難したい人は避難すればいいし、とどまりたい人はとどまればいいのです。放射線防護の専門家としては、居住を選んだ人に自衛手段を伝える必要があります」
――そのためにも情報公開が重要です。しかし、あなたはお金の出どころや組織の情報については何ら開示していません。
「ここまでにしましょう」
◇
Jacques Lochard 1950年生まれ。放射線防護の専門家、経済学者。ICRP副会長。フランスのNPO、原子力防護評価研究所(CEPN)ディレクター。
◆
(ジャーナリスト・藍原寛子、核と人類取材センター・田井中雅人)
あいはら・ひろこ ジャーナリスト、Japan Perspective News株式会社代表。元・福島民友新聞社記者。米マイアミ大学移植外科客員研究員、IFJ国際ジャーナリスト連盟メンバー、日本医学ジャーナリスト協会メンバー。
たいなか・まさと 中東アフリカ総局(カイロ)、国際報道部デスク、米ハーバード大客員研究員などを経て、核と人類取材センター記者。